ワンガリ・マータイ
 私は政府の人間でもなかったし、お金も持っていませんでした。でも、穴を掘ることはできました。
私は政府の人間でもなかったし、お金も持っていませんでした。でも、穴を掘ることはできました。

Illustrated by KIWABI - Wangari Muta Maathai
2004年にノーベル平和賞を受賞し、「モッタイナイ」の精神を世界に広めたことで知られるワンガリ・マータイは、砂漠化が進む母国ケニアに木を植えることで豊かさを取り戻そうとNGO「グリーンベルト運動」を立ち上げた中心人物です。
約40年前に7本からスタートした植樹はすでにケニアだけで5100万本に及び、ついにワンガリの目指した「国民1人につき1本」を達成、さらに森林率10パーセントを目指して、ワンガリ亡き後も続けられている活動は諸外国にまで波及しており、ケニアからアフリカ全土を含む少なくとも世界20カ国にまで広まりました。

↑国土の8割が乾燥しているケニアで3パーセント代まで落ち込んだ森林率が7パーセントまで持ち返した(リンク)
1984年に“もう一つのノーベル賞”と言われるライト・ライブリフッド賞を受賞して以降、運動への関心が高まると、ワンガリはよく「なぜ木なのですか?」と聞かれるようになったそうで、ワンガリはその答えを端的に「ただ問題を黙ってみていることはできなかったから」だとして、著書「UNBOWED へこたれない」の中で次のように述べています。(1)
「私は政府の人間でもなかったし、お金も持っていませんでした。でも、穴を掘ることはできました。穴を掘って苗木を植えることはできた。」

↑穴を掘ることにはお金も権力もいらない(リンク)
何も持っていなかったと語るワンガリは、かつて政府の奨学金でアメリカに留学し大学で教鞭もとっていたほどのエリートで、かつ、政治家の夫を支えていた妻でもあったのですが、男性社会のアフリカで、女性差別の色濃い大学や国民との約束を守らない政治の「腐敗」に立ち向かったことで反逆者とみなされ、結婚生活も仕事も家も、一気に失うことになりました。
そしてワンガリは「アフリカをだめにした犯人が高学歴のアフリカ人エリートであることは、まぎれもない事実である」と確信し、このとき唯一ワンガリに残っていたグリーンベルト運動の活動を前に、自分が間違っていると思うこと、そして正しいと思うことに正直であり続けるという決心を固くします。(2)

↑選挙戦は政治家と選挙区民が駆け引きするゲームでしかない。ゲームが終わったら政治家は約束なんて覚えていない(リンク)
グリーンベルト運動がスタートしたころ、すでにケニアを含めた多くのアフリカの人々は、ヨーロッパから持ち込まれた文化に染まり、象を見れば「象牙で商売ができる」と考え、チーターを見れば「美しい毛皮が売り物になる」と思い、自分たちの価値観をヨーロッパ人の貨幣経済のもつ価値観へと転換させられ、売れるとわかったらそれを守ることを忘れてしまえるようになってしまっていたそうです。
農民たちがコーヒーやお茶などの「換金作物」を育てるばかりになると、伝統的な自給自足の生活ではありえなかった栄養失調の人たちが増え、また、原生林の張り巡らされ根によって栄養が守られていた土壌は外国種を持ち込んだ産業植林によってもろくなり、雨が降れば土壌が侵食され、土からも栄養が失われていきました。
こういった事態を黙ってみていられなかったワンガリは、すべてを失ったときに自分自身を奮い起こしたように、グリーンベルト運動を、ひとりひとりが自分に正しい行動を起こす場にしようとしたのです。

↑原生林を失ったことで土も人も栄養を失っていった(リンク)
2007年から1年余りアマゾンの先住民の一族ヤノマミを取材したNHK取材班のチームは、昔のままの暮らしを続けるヤノマミは、富を貯め込まないし、また誇ることもないと言い、「ヤノマミ」というタイトルで出版されたその記録の中で、彼らの様子が次のように描写されていました。(3)
「どうして狩りに行かないのかと尋ねると、彼らは逆にこちらをバカにするかのような表情でこう言った。 『食べ物は十分に間に合っているのに、どうして獲りに行かねばならないのか』」
「昨日のことを一万年前のことのように話し、太古の伝説を昨日の出来事のように語った」と言うヤノマミの時間軸は今日明日で区切られていないのか、彼らの話はついさっき行った狩りの話から天地創造の神々の話までを行ったり来たりするのだそうで、そうして旧石器時代から大事なものを語り継いできた彼らのほうが「もっともっと」と考える社会に生きる人たちより、どこか宇宙の真理に近いところにいる気がしてなりません。

↑ヤノマミには権力者はいない
善悪や法律もない、でも万物に精霊が宿っている(リンク)
かつてアマゾンの先住民をたずねた沢木耕太郎氏は、先住民たちは「純なだけ汚れやすい」と述べていましたが、先住民を守るために武力で彼らの住む地域を封鎖するブラジル政府組織「国立インディオ基金」で総裁をつとめていたシドニー・ポスエロ氏によると、先住民にとって文明国の人間と接することがもっとも不幸なことなのだといいます。 (4)
「彼らは私たちと接触することで笑顔を失う。モノを得る代わりに笑顔を失う。」

↑白い色に黒い色が入るともう白くは戻れないように、ただ純粋に笑っていた頃にはもう戻れない、病気を知らなかった体にも戻れない(リンク)
ヤノマミの女性たちはタロイモやバナナなどの作物を作っており、畑で彼女たちはお喋りをしては笑い、飛ぶ鳥を見ては笑い、夫や家族の噂話をしては笑っていたと言いますが、ワンガリは、グリーンベルト運動を広める中で出会った、「貧乏だし、何かと病気を抱えているし、栄養失調でいつも飢えている」と不満を口にする多くの人たちに対して、政府のせいばかりにせず、自分自身のことも責めるべきだと次のように告げていたそうです。(5)
「あなたがたのものなのに、あなたがたは大事にしていません。土壌の浸食が起こるままにしていますが、あなたがたにも何かできるはずです。木を植えられるじゃないですか。」
「間に合ううちに声をあげ、立ち上がりましょう。大臣たちが聞いてくれないなら、大統領が聞いてくれるでしょう。大臣たちに無視されたなら、私たちの弱々しい声が大統領府に届くまで声をあげ続けるのです。大統領は環境保護主義者であると公言し、国民のことを大切に思っているからです。」

↑土地が痩せ、貧しくなっていくのは本当に政府だけのせいなのか?(リンク)
けれど、それはさながら政治活動のようで、苛立った大統領はグリーンベルト運動の資金集めを難しくさせ、政府内では「あの女を追い出せ、追い出せ」と盛り上がり、武装した政府部隊は暴行を加えてでもワンガリの行動を阻止しようとし始め、政府の人間はそんなワンガリの姿を女性たちに見せ、「おまえたちもこうなりたいのか」と知らしめようと躍起になったそうです。
ワンガリは、「大切なのは、そして必要なのは、自分の本当の姿を見るために、自分自身の鏡をかざすこと」として、政府が見せた姿ではなく自分自身を映す鏡を見つめてほしいという気持ちで女性たちに向き合い続けたと言い、1999年に行われたグリーンベルト運動のワークショップに参加したタンザニアの女性は「私たちは緑、この手から緑が生まれる」という詩を詠んで、次のように気持ちの変化について語りました。(6)(7)
「私たちは東からやってきた、肌の色は赤い
私たちは西からやってきた、肌の色は白い
私たちは南からやってきた、肌は黒いけれど
もうみんな緑になった、この手が触れたところから」
「ケニアも、タンザニアも
ガーナも、ウガンダも
ジンバブエも、エチオピアも、自分たちのものだなんて思わなかった
でももうわかる、この手から緑が茅生えることを」

↑この手ひとつで見える世界が変わっていく(リンク)
スワヒリ語で、「みんなの力を合わせよう!」を意味する「ハランべー」から、「セイブ・ザ・ランド・ハランベー」をスローガンに部族の壁を越えて取り組んだ農民の女性たちは、伝統的な技術と知恵、それに女の勘とネットワークを活かすことで、植物の開花時期を見極めて種を集め、種や苗木に家畜を寄せつけない方法を見出し、苗を育てるポットといった資源をリサイクルして最大限に苗を増やすなどの成功を遂げるうちに、自分でもできることがあると知るようになったのです。

↑古くからアフリカの大地に伝わるスワヒリ語の掛け声だったからこそ、女性たちは境界なく手を取り合えた(リンク)
「私たちが正しいことを行うのは、人々を喜ばせるためではなく、たとえほかにそうする人が誰もいなくても、自分自身に正直であろうとするなら、そうするしか論理的に筋が通らないからだ」というのは、30代で一度すべてを失って以降、ワンガリが大事にしてきた道理だと言います。そんなワンガリは、まず穴を掘って木を植えることからはじめ、運動が大きくなり武装した警官と緊迫した状況になると歌を歌い踊りを舞いました。(8)
たとえ大掛かりな戦略を立てられなくても心の動くままに行動することができ、敵対する人が現れてもどこか楽観的に、反撃か降伏を選ばないでトラブルを回避してしまう力は、女性ならではの強さなのではないでしょうか。
きっと私たちは真理に気づいていながら一人では無理だと行動を先延ばしにしてしまうのですが、「読めない」行動に周囲から疑問を持たれつつも、無理なくできる小さなことからやってみながら臨機応変に対応していくだけで、自分に正しい行いをすることは意外と難しくないのかもしれません。
1.ワンガリ マータイ 「モッタイナイで地球は緑になる」 (木楽舎 2005年) p265
2.ワンガリ マータイ 「モッタイナイで地球は緑になる」 (木楽舎 2005年) p163
3.国分拓 「ヤノマミ」 (NHK出版 2010年) Kindle
4.国分拓 「ヤノマミ」 (NHK出版 2010年) Kindle
5.ワンガリ マータイ 「UNBOWEDへこたれない ~ワンガリ・マータイ自伝」 (小学館 2007年) pp287,309
6.ワンガリ マータイ 「UNBOWEDへこたれない ~ワンガリ・マータイ自伝」 (小学館 2007年) pp318-9
7.ワンガリ マータイ 「モッタイナイで地球は緑になる」 (木楽舎 2005年) pp202-6
8.ワンガリ マータイ 「UNBOWEDへこたれない ~ワンガリ・マータイ自伝」 (小学館 2007年) p275
■ 沢木 耕太郎「イルカと墜落」(文藝春秋 2009年)






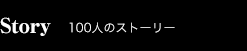



















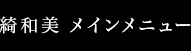
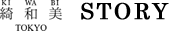
 私は政府の人間でもなかったし、お金も持っていませんでした。でも、穴を掘ることはできました。
私は政府の人間でもなかったし、お金も持っていませんでした。でも、穴を掘ることはできました。