長谷部 誠
 『自分を殺すこと』と『自分を変えること』は違う
『自分を殺すこと』と『自分を変えること』は違う

Illustrated by KIWABI - Makoto Hasebe
ドイツのプロサッカーリーグには今季、“地殻変動”のようなものが起きていて、シーズンの半分が終了した2017年1月現在、いつもの上位常連チームが苦戦しており、その中で降格寸前といわれていたチーム「フランクフルト」がリーグ4位に上り詰めています。
実はこのフランクフルトには、2013年にドイツに渡った日本の長谷部誠選手が所属していて、攻めと守りのスイッチを切り替えて体勢を整える“バランサー”の役目を担っています。そのプレーの様子は、「そこに長谷部がいることでチームが落ち着く、そんな印象だった」とレポートされており、フランクフルトのスポーツ部門取締役フレディ・ボビッチ氏は長谷部を「真のリーダー」であり、「我々のパズルにおける大事なピース」と評しました。
一方日本では、Jリーグで活躍していたころの長谷部はドリブルで仕掛けていく華やかなプレーが強みであったため、ドイツの長谷部はなんだか別人のようにも見え、日本のファンは「もっと攻撃的なプレーを」と期待を募らせていた時期があったことも事実です。

↑ゴールへと近づいていく選手の姿は脳裏に焼きついてしまう(リンク)
ドイツに渡ってからの長谷部は、自分には相手を置き去りにするほどのスピードはないし、パスにおいてもたとえば中村俊輔氏のように意表をつく華麗なパスをコンスタントに出せるわけでもない、つまりプロとして生き残るために「自分の強みはわかりづらい」という現実を見据え、何か自分の武器と言えるものはないかと追求しました。そして、自分が勝負できるところを総合力と定めると、「組織に足りないものを補う」ということが強みを生かす方法だと見込み、次のような努力をして生き残ろうとしてきたそうです。(1)
「中盤から攻め上がる選手がいたら、自分は中盤に留まって相手のカウンターに備える。みんなが疲れてきて動きが落ちてきたなと思ったら、人の分までカバーして走る。」

↑チームにできた隙を敵よりも先に見つけて埋める(リンク)
昔の長谷部のプレーに感動してきたファンたちの目には、ドイツの長谷部は自分らしさを消して我慢してプレーしているというように映っていたかもしれませんが、長谷部自身は、『自分を殺すこと』と『自分を変えること』は違い、ドイツに来てから自分が変わったことは正解だったと語っています。(2)
長谷部は「変化を受け入れなければ進化することはできない」とも述べていますが、もともと欧米で生まれた「Evolution(進化)」という言葉も、本来、「進歩する」という意味ではなく、単純に「変わる」という意味なのだそうで、変わることには悪くなることもあるし良くなることもあるけれど、結局は生き残ったものが正しかった・進化したと言えることになっているのです。
肥満遺伝子や薄毛遺伝子と言われるように、遺伝による影響は大きいと思い込まれがちですが、実際、性格や能力においては育った環境が左右する割合が、文章力で86パーセント、率直な性格かどうかは50パーセント、外交的か内向的かは60パーセント近くにもなるそうで、私たちは「生き残る」という全生物に通じるミッションを遂げるため、自分でも無意識のうちにその環境でベストなように変わることを選んで生きているのかもしれません。(3)

↑文章力は遺伝する割合がたったの10パーセント強、社交的になるのも半数以上が育ちによるもの(リンク)
例えばオタマジャクシは、自分を丸飲みにするサンショウウオの子供がいる環境では、サンショウウオの口に入らないように頭を2倍に大きく膨らませ、また、そこにいる天敵がヤゴの場合は、強いアゴで噛みつかれればひとたまりもないので、頭を大きくするのではなく尾ひれの筋力をアップさせて逃げ足を速くするというように変わるほど、柔軟性があるのだそうです。
それはオタマジャクシが生き残りのために遂げた変化ですが、こういった捕食される生き物たちの「食べられないための知恵」を調べてきた進化生物学者の宮竹貴久氏によると、人間社会でもまさに生物学的に正しい生存戦略をとられていることが多いのだとして、次のように述べています。(4)
「ライバルを見比べて、『一番になれる可能性はあるか』を考えるのだ。 勝てないライバルがいる場合には、いまのやり方で何番手までが生き残れるかを推し量る。あるいは、一番手の取り巻きになることができるかを模索する。そして、それらがどれも困難だと判断したときには、新興市場に打って出るしか道は開けない。 」

↑今の環境で生き残りが難しければ新天地へと動くのは生物学的に正しい(リンク)
10年ほど前に「僕は、ひな壇に出ません」と宣言し話題を呼んだお笑いコンビ、キングコングの西野亮廣氏は、ひな壇に座っている芸人たちは「0コンマ何秒を争う居合抜きの達人のような人」ばかりで、自分の能力は彼らとは程遠く、努力をして能力をちょっとアップさせたところで自分に勝ち目はないと見切りをつけ、勝ち目のあるところを120点に伸ばすほうを選んだのだそうです。
そういった考えの根っこには、出演していたテレビ番組「はねるのトびら」がゴールデン枠になっても自分はスター芸人にはなれなかった、突き抜けたところがない平凡な自分に気づいたところにありました。そして、自分をスターに進化させるもっとも有効な方法として、思い切ってテレビに出るのをレギュラー番組以外は全部やめると決断し、そこに至った理屈を普通の人が当たり前に使っている「腕」を切り落とすという例えを出して、次のように説明しています。(5)
「皆が使っている一番便利な部位は、当然、自分にとっても便利な部位なので、そこを切り落としてしまうと、最初は、それはそれは苦労するけれど、僕らは動物で、それでも生きようとするから、3年後には、コップぐらいなら足で持てるようになる。足でコップを持てる奴なんて、そうそういないから、『アイツ、足でコップを持てるらしいよ』と、この時、初めて自分に視線が集まる。」
それから彼はお笑い以外でも純粋にお客さんを楽しませるエンターテイメントにこだわって、飛びぬけて手の込んだ絵本をつくるなどを手がけ、「エンターテイメントが人間を感動させている瞬間だけは世界は平和でいられる」という考えに至ると、ついつい面白いことがつながって1日の行動をコーディネートできてしまうような街づくりをしようとプロジェクトをスタートさせています。

↑祭りを見て温泉に入って、次の日はライブに行こう(リンク)
西野亮廣氏がテレビ出演を絶ったとき、「そうでもしないと、何者にもならないまま死んでしまうという焦りがあった」と述べていますし、進化生物学においても、「死んだふり」をすることがうまくなって生き延びる確率を上げた個体は、それと同時に活動量を抑えたことでメスと出会いづらくなり繁殖の機会を減らしてしまうことが確認されていますから、生き残ろうと変わることは大きな犠牲を払うことと背中合わせなのかもしれません。(6)(7)
長谷部も「チームの穴を埋める」ということは成果としてわかりやすい仕事ではなく、契約更新の話し合いの際に「プレーが印象に残っていない」と言われたこともあったと述べていました。
バランサーというとカッコよく聞こえますが、直接自分で点を取りに行くといった派手なパフォーマンスをしないため、じっとプレーを見ていてもらえないと気づかれず、存在意義を疑われかねない役目でもあります。そこで、「90分間ポジショニングを見続けてほしい」という話をしたところ、相手のディレクターから、「組織に生まれた穴を常に埋められる選手だ。とても思慮深くプレーしているし、リーグ全体を見渡しても彼のような選手は貴重だ」と評価され、契約延長となったそうです。(8)

↑ボールを追うのではなく、自分の動きを追いかけてくれればわかる(リンク)
チームの穴を埋めると評価された長谷部が2016年秋から任されるようになってきたのはリベロというポジションで、リベロとは敵の中にマークすべき特定の選手を持たないディフェンダーを指し攻撃にも参加しますが、このポジションが確立する前までのディフェンダーはたとえ特定の敵をマークしていなくとも、「敵の前に立ちふさがり、鉄の足で掃除をすればよい」と役目が固定されていました。
攻めも守りもできるリベロを世間に認めさせたのは1970年代を中心に活躍し、2006年FIFAワールドカップドイツ大会で組織委員長を務めたドイツのフランツ・ベッケンバウアー氏で、彼は自伝の中で、「リベロ=自由なディフェンダー」になりたかった理由を、攻撃は自陣のディフェンスあたりから始まるものだし、そこからは敵チームの穴がよく見え、同時に自分のチームの穴もよく見える、つまり攻撃を組み立てるのも守りを修正するのも可能だからだと述べています。(9)

↑攻撃のスタートの場にいるディフェンスが守るだけなんてもったいない(リンク)
あるフランスチームを調べたところ、「1人の選手がボールに触れる時間の平均は53.4±8.1秒」と、通常選手は試合時間90分のうちボールに触っているのは約1分で、89分はボールに触っていないことが明らかになっていますが、試合の中でリベロをつとめていたベッケンバウアー氏は、5分以上ボールに触っていたそうです。
リベロというポジションが受け入れられる前の5年間、チームの監督さえも「楽なポジションを選んでいる」と批判的だったものの、ベッケンバウアー氏の説得は受け入れられ、正式にリベロとして国際試合に出場できるようになると、功を奏したリベロ戦術は人々を歓喜させ、「ドイツといえばリベロ」と言われるようになりました。(10)
その後新しい戦法が普及し、個人の能力に大きく左右されるリベロを置く戦法は下火になりましたが、長谷部によってリベロが再び脚光を浴びつつあり、ドイツのスポーツ専門家から「彼は日本のベッケンバウアーだよ!」という期待のコメントが寄せられています。

↑ドイツから世界へとまたリベロのサッカーが始まるかもしれない(リンク)
かつて長谷部とともに日本でプレーをしていた人たちは、 「ハセさんはドイツに行ってからプレーが変わった。それを見て自分も海外に挑戦したくなった」と言うようになり、自分を変えようと動き出した選手もいて、たとえば岡崎慎司氏はドイツのシュツットガルトに、矢野貴章氏はドイツのフライブルクへと渡りました。(11)
「生物の原点。それは『生きて、つなぐ』である」と、前出の進化生物学者の宮竹貴久氏は述べていますし、うまく生き残った先にはその変化の正しさに気づき、ついてくる人たちが現れてつながっていくのが、どうやら生物界のルールのようです。(12)
目立たなくなってでも、頭が2倍になってでも、死んだふりがうまくなってでも、何かほかより優れているところがあるようにと融通を利かせることで生き残れるのですから、たとえカッコ悪くなる方法を使っても「生きて、つなぐ」ことができればそれは生物学的に大正解で、いつの間にかカッコいいと広まっているものなのかもしれません。
1.長谷部誠 「心を整える。 勝利をたぐり寄せるための56の習慣」 (幻冬舎 2014年) Kindle
2.長谷部誠 「心を整える。 勝利をたぐり寄せるための56の習慣」 (幻冬舎 2014年) Kindle
3.宮竹貴久 「「先送り」は生物学的に正しい 究極の生き残る技術」 (講談社 2014年) Kindle
4.宮竹貴久 「「先送り」は生物学的に正しい 究極の生き残る技術」 (講談社 2014年) Kindle
5.西野亮廣 「魔法のコンパス 道なき道の歩き方」 (主婦と生活社 2016年) pp46-7
6.西野亮廣 「魔法のコンパス 道なき道の歩き方」 (主婦と生活社 2016年) pp48
7.宮竹貴久 「「先送り」は生物学的に正しい 究極の生き残る技術」 (講談社 2014年) Kindle
8.長谷部誠 「心を整える。 勝利をたぐり寄せるための56の習慣」 (幻冬舎 2014年) Kindle
9.フランツ ベッケンバウアー 「ベッケンバウアー自伝―「皇帝」と呼ばれた男」 (中央公論新社 2006年) p18
10.フランツ ベッケンバウアー 「ベッケンバウアー自伝―「皇帝」と呼ばれた男」 (中央公論新社 2006年) p19
11.長谷部誠 「心を整える。 勝利をたぐり寄せるための56の習慣」 (幻冬舎 2014年) Kindle
12.宮竹貴久 「「先送り」は生物学的に正しい 究極の生き残る技術」 (講談社 2014年) Kindle






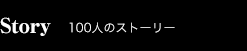



















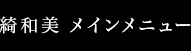
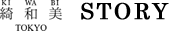
 『自分を殺すこと』と『自分を変えること』は違う
『自分を殺すこと』と『自分を変えること』は違う