宝塚の品格を築いた男:小林一三
 人に頼ることは失敗の第一歩である 小林一三
人に頼ることは失敗の第一歩である 小林一三

阪急電鉄を起こし、鉄道の走るところに街をつくり上げ、住む人の生活を彩るターミナルデパートや宝塚歌劇団を生み出した小林一三(こばやし いちぞう)は、戦後にGHQと対等に渡り合って外交を行った白洲次郎までもが「こんなに頭のいい人は見たことがない」と言うほど、超人扱いされていた起業家でした。
そんな小林一三は、「美しくはないが、無理をせず、焦らず、堅実に着々と進むことが勝利に導く」と説き、新しい事に着手するかどうかを決めるには、納得いくまで一年でも二年でも研究するという人だったらしく、彼の残した次のような言葉にもその考えが表れています。(1)
「最後に頼むものは自分以外には決してあるものじゃない。やりたい仕事も自分の力量以上に手出しをしたら、みじめな終局があるばかりだ。」
事実、日比谷劇場の建築を中心に日比谷をエンターテイメントの街としてデザインした事業においても、小林一三は事業に着手する10年も前に名古屋で売りに出ていた国技館を参考にするなどして経済的な建築方法について思案し始めており、さらに、日比谷や銀座の交通機関を利用する人たちを詳しく調べ、浅草など東京にある劇場や映画館の入場者の統計をとるといった研究に研究を尽くし、「これなら大丈夫」という確信をもとに事業を進めたと言われています。

↑小林一三「決して思いつきでオイソレと建てたものではない」日比谷・銀座を研究し尽くした結果だ(リンク)
そんな小林一三ですが、鉄道事業を思いつく前に銀行でサラリーマンをしていた時代には、「安い給料でいかに遊ぶか」ばかりを考えていて仕事に必要な事務能力はゼロに近く、恋愛沙汰で3ヶ月も無断欠勤したこともあり、さらには、自分は将来小説家になるものと信じていたロマンチストでもあって、社会人としては絵に描いたようなダメ男でした。
ある日、大阪の田舎道を歩きながら、大阪市内に急増する人口を支える新しい鉄道によって人々が郊外に広がり街がつくられる絵が思い浮かび、はじめて全身からやりたいという気持ちが湧いたそうですが、それでも小林一三は鉄道事業ををスタートしてからもしばらく、当時の主流路線であった阪神電車と合併すれば「阪神電車の重役になれると内々期待していた」と、楽な方に心が揺らいでいたことを吐露しています。

↑地道な努力しかない青二才の小林一三には「重役」という役職が眩しかった(リンク)
結局、阪神電車との合併が思い通りにいかなかった小林一三は人に頼ることをやめ、小説家を目指していた持ち前の発想力と文章力で、田舎を走る電車に「ガラアキで眺めの素敵によい凍しい(すずしい)電車」というコピーをつけて印象付け、続けてその沿線に住宅地をつくると、今度は「美しき水の都は昔の夢と消えて、空暗き煙の都に住む不幸なる我が大阪市民諸君」と大衆に呼びかけて自然豊かな郊外をブランド化するなどし、人々の心をさらっていきました。(2)
世界初となるターミナルデパートをつくった後、その食堂の宣伝に、「当店はライスだけのお客さまを、喜んで歓迎いたします」という新聞広告を打ったのも小林一三のアイデアで、食堂に雰囲気だけを味わいにくる利益の薄い若い顧客が子供を連れてくる未来を見通していたのです。(3)

↑ライスしか頼めないカップルも、10年後にきっと子供のために注文するようになる(リンク)
小林一三が自分の足で進むようになったのには、1914年に北浜銀行が倒産し、小林一三の起業支援者で財界の重鎮であった岩下清周(きよちか)が横領などを疑われて逮捕・投獄されたことがきっかけでもありました。一時の勢いで事業に手を出してはいけないと気持ちを引き締めた小林一三は、「無理をするな」ということをすべてに通じてモットーにするようになり、大きな事業の話が舞い込んできても、確証のもてないことからはあっさりと手を引いていたそうです。
小林一三と親しかった友人の一人で、「電力の鬼」と呼ばれ、日本の高度経済成長を支える電気事業を成し遂げた松永安左ェ門(やすざえもん)は、起業家としての小林一三の性格には一言であらわすと「のぼせない、あせらない、動揺しない」という特徴があるとしていました。
福沢諭吉が起こした新聞「時事新報」は、1955年に廃刊する以前に、事業家たちが集まり援助を決め、福沢先生の恩に報いるべきという流れがあったそうですが、ただ一人、小林一三は「福沢先生の仕事だって、潰れるときがくれば潰れるよ」と手を引いたのだそうで、安左ェ門はそういった小林一三の独立した精神こそが“ 独立自尊” を説いた福沢諭吉スピリットを継ぐことなのではないかと思ったそうです。

↑成功と失脚は実は隣り合わせにあることを忘れてはいけない(リンク)
どれだけの成功を収めても、のぼせあがることなく几帳面で率直だったという小林一三は、「私が今日、東電を栄えさせ、阪急、東洋製罐(せいかん)、東宝などの事業をコントロールできているのは、私が物事を他人より先に知っていても、金を儲けたことがないからだ」と述べています。(4)
たしかに創業時の宝塚歌劇団をふりかえっても、初期に入団した娘の親は与えられる給与額の高さに娘が外国に売り飛ばされるのではないかと思ったというほどで、つい20年前まで、宝塚は阪急電鉄社内で赤字続きの不良債権事業部だったのだそうですが、それでも、小林一三が宝塚に見込んだ価値にふさわしい投資を続けたことで、初回公演から100年、小林一三の逝去から60年経ち、3つの専用劇場で年間900回以上もの公演をする大事業へと成長しました。
さらに、未来のタカラジェンヌを育てる宝塚音楽学校の2016年度の入試倍率は27倍、「人の悪口は言わない」「コンビニに行かない」など日常をタカラジェンヌ仕様に変えてまで宝塚音楽学校を目指すような少女たちが全国から集まり、世間から最難関の学校だといわれるほどのブランド力を持つようになっています。

↑「やばい」「うざい」も使わない、頭の中は24時間宝塚(リンク)
「無理をしない」は小林一三にとって宗教のようなものだったと言いますが、彼が自分の力や勘を過信せず、地道に研究を重ね事業に尽くしてこなかったら、よりリスクの大きい誘いに乗って破綻していたかもしれませんし、無責任にルールを破ってでも近道を選んでしまい、起こした事業を次世代にわたって長期的に成長させることはなかったでしょう。
IT企業の楽天の考え方には、今の自分を1としたとき、1パーセントのちょっとした努力でも1年間365日積み重ねると37倍になるという法則があるそうです。1%の努力とは逆に毎日1パーセント楽をすると、99%の状態が365日毎日積み重なり、1週間で93%、1ヶ月で73%、365日経つと残った数字は3%、つまり今の自分の力が100分の3にまで減ってしまうことになるのです。
今より1パーセント努力することと1パーセント楽をすることには1.01-0.99=0.02(2%)の差しかないのに、これを会社に置き換えれば1年後には37倍とほとんど何もない状態にまで差がついてしまう結果になるのかもしれません。

↑小林一三「新しい情報だけが生きているのではない。昨日、今日、明日につながる情報のみが有益なのだ。」(リンク)
慶應義塾大学の琴坂将広准教授は、この法則において1パーセントの努力を繰り返し続けることができるかどうかというのが1番のポイントなので、その努力のペースは自分で決めたほうがいいのだと、次のように述べました。
「例えば、卒業した時点でいい会社に入るっていうんだったら、ダメだったらいいじゃん。30歳でいいじゃん。30歳でダメだったら40歳でいいじゃんって。僕も留学しようとしたのは17歳とかで、できなかったです。できなかったけど、諦めないで10年やったらオックスフォード行けたんですよね。そういうふうに自分のペースでちょっとずつ挑戦し続けるってことをやってほしい。」

↑自分のペースでちょっとずつ挑戦し続けることで未来が変わる(リンク)
もともとは楽なほうを選ぶのが得意で、縁故で周囲に寄りかかり助けられ若かかりし頃を乗り切ってきた小林一三は、自分で着実な仕事をするようになって以降、「人に頼ることは失敗の第一歩である」と語るようになりました。
「年収5割アップ」「役員待遇」などといった甘い言葉に誘われて転職を決めた後、希望通りに会社が成長せず転職先の会社ごと転落していく人がいるように、人の力を計画に組み込んで高い目標を達成しようとするよりも、自分が継続する努力のほうが何倍も信用できるものなのです。
商品やサービスにおいても、「24時間で効果がわかる!」といったものは現れる効果の速さ・大きさに比例した副作用のあるものが多く見受けられる昨今、すぐに実を結ばないことに向かい、今日より1パーセントよくなろうと黙々と堅実に努力することを選ぶ人だけが、地面を見つめて登っているうちにいつの間にか成功の山の頂に到達できるのかもしれません。
1.北康利 「小林一三 時代の十歩先が見えた男」 (PHP研究所 2014年)p107
2.小島直記 「鬼才縦横 〈下〉―小林一三の生涯」 (日本経済新聞出版社 2012年)p62
3.北康利 「小林一三 時代の十歩先が見えた男」 (PHP研究所 2014年)p149
4.北康利 「小林一三 時代の十歩先が見えた男」 (PHP研究所 2014年)p184
■ 小島 直記「鬼才縦横 〈上〉―小林一三の生涯」(日本経済新聞出版社 2012年)
■ 小林一三翁追想録編纂委員会「小林一三翁の追想」(佐藤博夫 1961年)
■ 三木谷 浩史「成功のコンセプト」(幻冬舎 2009年)






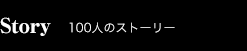



















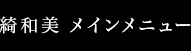
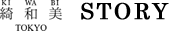
 人に頼ることは失敗の第一歩である 小林一三
人に頼ることは失敗の第一歩である 小林一三