チャールズ・チャップリン
 笑いとは、すなわち反抗精神である。
笑いとは、すなわち反抗精神である。

Illustrated by KIWABI - Sir Charles Spencer Chaplin
喜劇王として世界中で親しまれ、数多くの作品を世に送り出してきたチャールズ・チャップリン。
チャップリンは、生涯で残した80作を越える映画の中で自分自身で出演、製作、劇中に流れる音楽の作曲、そして脚本といった、全てを行いました。
このことについて、イギリスの映画評論家デイヴィッド・ロビンソンはチャップリンについて次のように述べています。(1)
「チャップリンは全生涯にわたり、すべてのことを自分ひとりの力でなし遂げたいという強い衝動に突き動かされていた。その思いは自らの映画それぞれのあらゆる役割を全部ひとりでこなしたいと望むほど強かった。」

↑チャップリンは亡くなった後でも多くの人を魅了し続ける存在(リンク)
故郷であるイギリスを離れ、アメリカで俳優として大成功し、当時で週給が1万ドルを超える(現代の価値でおよそ2800万円相当)ような報酬を得ていたチャップリン。
子供時代を振り返ると、そこに住む子供たちの3分の1が命を落とすと言われるほどの貧困地区で孤児院を転々として暮らし、生活を支えるために劇団員を始め、様々な仕事を経験しています。
また、父親をアルコール依存症で亡くし、母親は貧困に耐えきれず精神病を患ってしまうなど、このときに経験した生涯で一番最悪だった生活や生きるための知恵は、役者として大成功をおさめるための糧となっていたのだそうです。

↑チャップリンが子ども頃に培った経験はのちの大成功への糧となった(リンク)
ブカブカなズボンを履いてコミカルな動きで映画を観る人を楽しませ、「モダン・タイムズ」のような映画にも出演する放浪紳士チャーリーについても、チャップリンはこのように語りました。
「ただ人を笑わせるだけが喜劇じゃないことは確かだ。わたしの思いを表現するなら、わたしという人間を培ってきた社会を表現しなければならない。スクリーンの中の出来事は現実の社会と関わっているのだ。少なくとも『チャーリー』はそうだ。」
労働者を機械の一部のように扱う時代の変化への不快感を表した「モダン・タイムズ」は、チャップリンの作品の中でも代表的な存在です。
そうしたチャップリン独特の表現を、映画プロデューサーでありチャップリン研究家としても知られる大野裕之氏は、「卓越した身体芸で笑顔にして、その哀愁に満ちた姿で涙をあふれさせ、鋭い社会批評で問題を提起し続けている」と表していました。(2)

↑思いを表現するなら、培ってきた社会を表現しなければならない(リンク)
自分の主張にユーモアを加え、喜劇として表現することについて、チャップリン自身も次のように語っています。(3)
「逆説かもしれぬが、しばしば悲劇がかえって笑いの精神を刺激してくれるのである。思うに、その理由というのは、笑いとは、すなわち反抗精神であるということである。わたしたちは自然の威力というものの前に立って、自分の無力ぶりを笑うよりほかにない。笑わなければ、気がちがってしまうだろう。」
チャップリンの生きた時代は戦争が起き、経済も不安定で、現代のような落ち着きとは程遠い時代でした。
そうした時代の流れや運命といった、自分一人の力ではどうにもならないことに押しつぶされ、すべてを呪ってしまうよりも、自分の無力ぶりを喜劇による笑いの力で反抗していたのかもしれません。

↑笑いとは反骨精神で、どうしようもないときは自分の無力ぶりを笑うよりほかない(リンク)
チャップリンが俳優や監督として多くの作品を生み出せた背景には、自分自身の人生で経験した辛さや幸せがあったからで、そのような経験をした自分にしかあのような作品は生み出せないとして、次のように述べています。(4)
「わたしは、わたしでしかない。ひとりの個人、他人とは異なる唯一の存在で、先祖からの刺激と促しにかられた人生、すなわち、夢と憧れと特別な経験に満ちた人生を送ってきた。それらをすべて合計したものがわたしなのだ。」
それだけにチャップリンは自分の作品に対して強いこだわりをもっていました。
例えば、「街の灯し」という映画では、映画の撮影期間が1年半のところ、主人公とヒロインが出会うという数分のシーンに納得がいかず、そのシーンを作るためだけに1年以上かけたとも言われています。

↑無力感を笑いに変え、自分の思いを映画で表現し続けた(リンク)
映画を何度も撮り直したというエピソードからわかるように、完璧主義者である一方で、チャップリンは自分自身の性格を内向的で人見知りだと言っていました。
内向的な性格の持ち主であったことで、チャップリンはどんな環境にあっても、自分の思いに忠実になることができたから、自分の中にある意見や思いを社会に訴えることができたのかもしれません。
自分ではない誰かの思いに従うよりも、自分自身が何を思って生きているのかに耳を傾け、表現していくことが、他の人からの共感や支持を得る近道なのではないでしょうか。
1. チャールズ・チャップリン 「チャップリン自伝: 若き日々」 (新潮文庫,2017) p.9
2. 大野裕之 「チャップリン 作品とその生涯」(中央公論新社,2017)p.3
3. 大野裕之 「チャップリン 作品とその生涯」(中央公論新社,2017)p.168
4. チャールズ・チャップリン「チャップリン自伝: 若き日々」(新潮文庫,2017)p.20






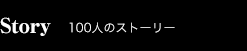



















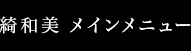
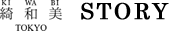
 笑いとは、すなわち反抗精神である。
笑いとは、すなわち反抗精神である。