山口絵里子
 フェアトレードはフェアじゃない。途上国初のブランドを創る 。
フェアトレードはフェアじゃない。途上国初のブランドを創る 。

Illustrated by KIWABI - Eriko Yamaguchi
人口の約40%が1日1ドル以下で生活するアジアの最貧国、そして政治汚職度世界ワースト1位の国でもあるバングラディッシュで、当時23歳だった実業家の山口絵里子は起業することを選びました。
100% “Made in Bangladesh”のバッグブランド「MOTHER HOUSE」を築いた山口絵里子が、そのブランド確立に至るまでの道のりは本当に長くて険しいものだったようです。
現地の製造業者からはまったく相手にされず、やっとの思いで作ったサンプルは思い描いていたものから程遠く、挙げ句の果てには山口が徹夜で考えたデザインを他の会社に勝手に売られてしまうなどといった難題の数々に対して、彼女は「社会に対する思い」ひとつで立ち向かっていったのでした。

↑「世の中を変えたい」誰が何と言おうとこの思いを貫く(リンク)
小学校の時にいじめを受けた山口は、自分の気持ちに理解のない教師に憤り、中学生になると非行を繰り返していましたが、その経験から、社会が作った教育システムに問題があるからいじめや非行が生まれるのだと考え、政治家になることを目指して大学へ進学します。
しかしながら、どれだけ勉強しても他の学生との差が一向に埋まらないことに、とてつもないコンプレックスを抱き、それでも無理して勉強し続けたことで彼女は身体を壊してしまいました。
そこであらためて自分は何のために生きていているんだろうと考えてみると「もっともっと社会を良くしたい」「社会を変えることが私の存在意義」という思いに気づくことになったのです。(1)
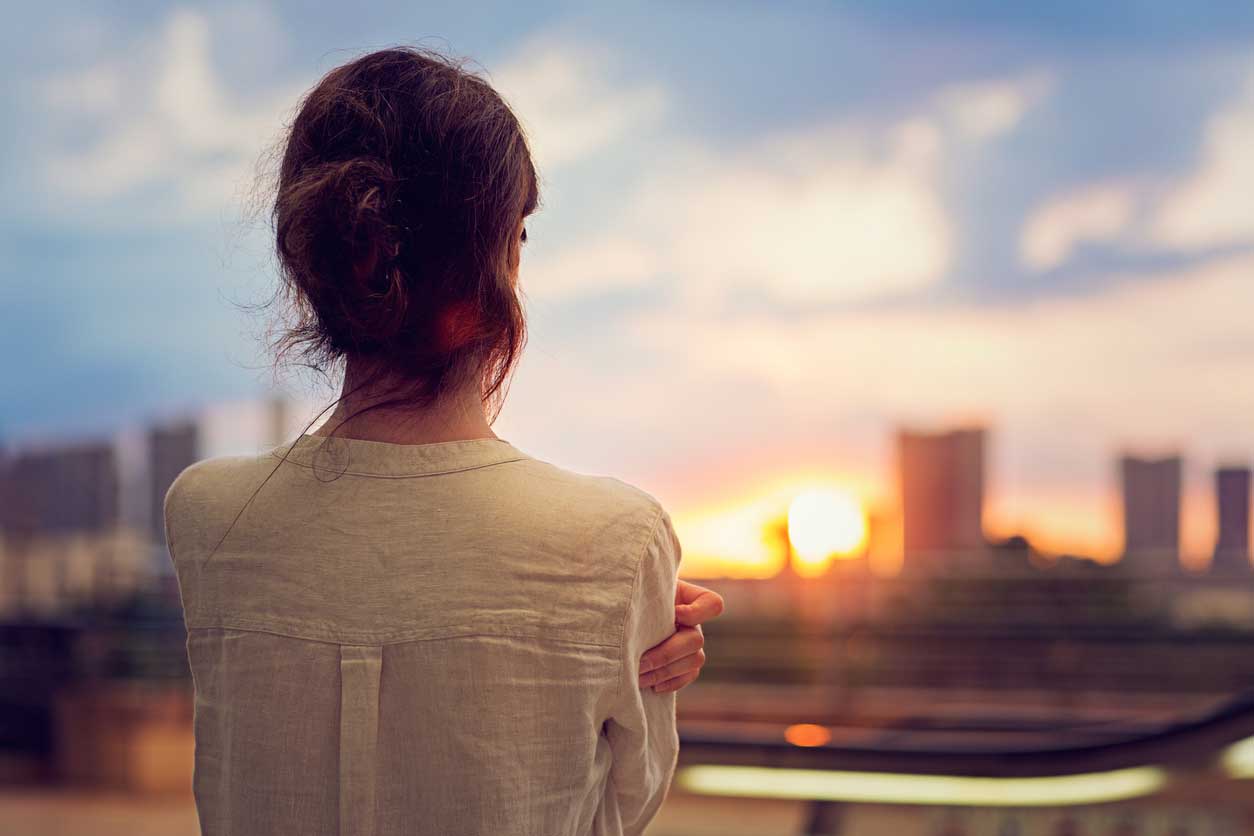
↑生きる目的は今の社会を変えること(リンク)
大学で開発学を勉強するようになった山口は「発展途上国は先進国に技術を倣うことで先進国との格差を縮められる。しかし、現実には多くの問題によってその格差は広がっている」と書かれた教科書の内容にどうしようもない疑問を覚えます。(2)
この疑問をきっかけに「発展の障害となっているものはなんだろう」「成長のモデルは1つなのか」「自由貿易は発展を促進するのか」と、開発問題を抱える現場への思いを強くしていきました。(3)
大学4年時にワシントンの米州開発銀行という国際機関で働くチャンスを得た山口は、現場のことは他人に任せ、自分たちは頭だけ使えばいいといった態度で働く人たちを目の当たりにすると、実際に途上国へ行って、そこで何が起こっているのかを自分の目で確かめようと決心します。
そして、初めて訪れたバングラディッシュで目にしたのは、ゴミの山をあさり、汚染によって緑色に染まった川で洗濯をする人々の姿で、現場にいなければ分からないことがたくさんあると気づいた山口は、そのままバングラディッシュの大学院へ進学することを決めました。

↑本当の貧しさは目で見てみないと分からない
バングラディッシュの人々の暮らしが貧しい理由の1つには、大量に生産した安価な製品を先進国のバイヤーに買い叩かれているといったことがあります。
それに対して世間ではフェアトレードと呼ばれる取り組みが行われるようになりましたが、その商品の多くが、品質ではなくかわいそうだからという同情心によって買われていることに山口は強い疑問を抱いていました。
ある時、彼女はジュートと呼ばれるバングラディッシュ名産の天然繊維に注目すると、このジュートを使って、消費者が心から「かわいい!欲しい!」と思ってもらえるバックが作れないかと考えたのです。
それは、NGOや支援という形ではなくて、生産者が誇りとプライドを持ってバッグを作り、先進国の消費者がそのデザインや品質に満足して購入することのできる途上国初のブランドを創ることを決意した瞬間でした。

↑強い事業があれば貧困に打ち勝てる(リンク)
貧困者でもお金を借りることのできるグラミン銀行を創設し、ノーベル平和賞を受賞した経済学者のムハマド・ユヌス氏も、寄付や施しは、与えられる側の尊厳を奪い、自分で収入を得ようとする意欲すら奪ってしまうと語っています。(4)
「寄付するという立場でいる人たちは、本質的な課題から目を背けているだけに過ぎない」というユヌス氏の言葉通り、私たちはフェアトレード商品をつくる人や、寄付を受けとる途上国の人たちのことをもっとよく知ろうと努力しなければ、彼らとフェアになりたいと心から願うまでにはなれず、結局は善い行いをしているという自己満足を高めるだけになってしまうのかもしれません。

↑ビジネスを通じてお金を循環させると寄付よりも深い絆ができる(リンク)
NGO職員としてケニアの貧困や雇用問題と向き合っていた荻生田愛さんも、失業率が40%とも50%とも言われ、すっかり支援されることに慣れきってしまったケニアの人たちに「日本でケニアのバラをたくさん売れば、アフリカの雇用環境が改善されるかもしれない」と考えたそうです。
ヨーロッパへの輸出用に栽培されているケニアのバラの美しさに魅了されていた荻生田さんは、「ケニアの人を支援するため」ではなく「キレイだから」という思いからケニアのバラの販売を始めたのだとして、次のように述べました。
「フェアトレード商品を購入する時、商品の質に目をつぶっていないでしょうか?施し、施されるという関係では、フェアとは呼べないと思うのです。」

↑フェアであるとは弱者救済ではなくお互いを対等に扱うということ(リンク)
実際、途上国に生まれただけで貧困から脱することが難しくなるという世の中の仕組みを変えるには、同じ人間として対等な関係を築いていこうとする姿勢が大事であり、それを妨げるような支援ならしない方がずっとよいのかもしれません。
思えば、私たちの祖先が焼け跡から全てを始め、その日食べるものにも苦労する暮らしをしていたのはたった70年前のことです。そこからたった20年で粗悪品の代名詞だった“Made in Japan”を性能の良い工業製品の印へと変えていったのです。
山口は、「アメリカやヨーロッパの大学院に入ることよりも、いったい途上国の現場で何が起きているのか、この目で見る方がずっと大切だと思った」と述べています。(5)
この言葉を真摯に受け止めて考えれば、フェアな世界を実現するために必要なのは、ただフェアトレード商品を買うことではなくて、その作り手たちは本当に素晴らしいものを生み出すことができる人たちなのだと知ることなのかもしれません。
山口絵里子「裸でも生きvる ~25歳女性起業家の号泣戦記~」(講談社、2016年)Kindle 399
山口絵里子「裸でも生きる ~25歳女性起業家の号泣戦記~」(講談社、2016年)Kindle 432
山口絵里子「裸でも生きる ~25歳女性起業家の号泣戦記~」(講談社、2016年)Kindle 440-443
ムハマド・ユヌス、アラン・ジョリ「ムハマド・ユヌス自伝ー貧困なき世界を目指す銀行家」(早川書房、1998年)P53
山口絵里子「裸でも生きる ~25歳女性起業家の号泣戦記~」(講談社、2016年)Kindle 800






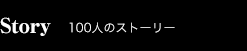



















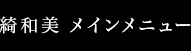
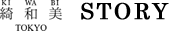
 フェアトレードはフェアじゃない。途上国初のブランドを創る 。
フェアトレードはフェアじゃない。途上国初のブランドを創る 。